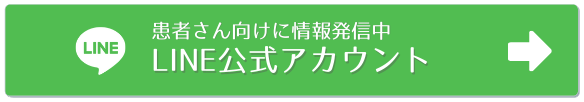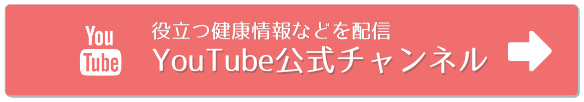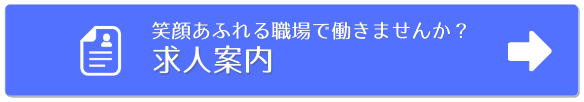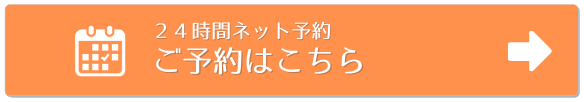![]() 糖尿病を予防するための食事ってどういうふうにしたらいいんですか?
糖尿病を予防するための食事ってどういうふうにしたらいいんですか?
![]() 糖尿病の薬を少しでも減らしたいけれど、そのための食事療法のポイントは?
糖尿病の薬を少しでも減らしたいけれど、そのための食事療法のポイントは?
![]() 血糖値を上げないためにはどうしたらいいか?
血糖値を上げないためにはどうしたらいいか?
上記のような悩みを持っている方は今回のブログがきっと役に立つと思います。
そもそも「血糖コントロール」とは?なぜ重要なのか?
こんにちは。医療法人社団 緑晴会 あまが台ファミリークリニック 院長の細田俊樹です。
私はプライマリ・ケア(総合診療)を専門に、医師として25年目になります。
私は年間延べ4,000以上の糖尿病患者さんをみています。
毎日糖尿病の患者さんを診察させていただいておりますが、患者さんの中には食事・生活習慣を改善し、服薬なしでコントロールが良好になられる患者さんもいらっしゃいます。
食事は毎日の積み重ねですので、糖尿病を予防改善するためにどういう食事のポイントを少し知っておくだけでも、5年、10年先の予防効果は大きく変わってきます。
食事は1日3回とるとして1週間で21回ですから1つ1つの食事のとり方によって病気になるかならないか、大きな影響を与えるというのは皆さんも感じていることと思います。

こちらのページでは、食事療法について解説していますので参考になれば幸いです。
目次
糖尿病の食事療法を一言でお伝えすると..「血糖を急激に上げるような食材、食べ方を避ける」ことです。
この食事基本について7つの項目に分けてご紹介します!
① 栄養のバランスの取れた食事をする
まずは、下記の5大栄養素のバランスをしっかりと整えることが重要です。

このバランスをしっかりと整えることで、糖尿病だけではなく、脂質異常症(高コレステロール血症など)や、高血圧症などの生活習慣病を予防・改善することにもつながります。
栄養バランスが偏っているな、と思われている方は、まずバランスの整った食事をしてみましょう。
 コツは、1回の食事の中で主食・主菜・副菜をそろえることから始めることです。
コツは、1回の食事の中で主食・主菜・副菜をそろえることから始めることです。
慣れてきたら小鉢・具の多い汁物を追加できるとなお良いです!
ただ、継続することが大切ですので、無理のない範囲でバランスの良い食事を心がけましょう。
② 腹八分を心がける
・ついつい勿体無くて食べてしまう
・お腹いっぱいまで食べる癖がある

という方は、まずは腹八分を心がけてみましょう。
腹八分を心がけていると、食欲をコントロールしやすくなり同時に血糖コントロールも安定しやすくなります。
ついついたくさん食べてしまう・・・という方は
 食事の前に水を1杯のむか、汁物を追加してみることもおすすめです!
食事の前に水を1杯のむか、汁物を追加してみることもおすすめです!
③ 食品の種類を増やしましょう
栄養素のバランスが偏ると、体に必要な栄養素がしっかりと取れなかったり、血糖値も安定しなかったり、糖尿病が進行してしまう可能性があります。
食品の種類を増やすことは、視覚的満足度を上げることもできるため満足感を得やすいと考えますし、私たちの体に必要な栄養素をバランスよく補いやすいです。
・冷奴
・納豆
・きゅうりのおかかあえ
・ほうれん草のおひたし
・もやしナムル
・ちくわきゅうり など


④ 食物繊維を多く含む食品を多く摂るようにしましょう
食物繊維を多く含む食材は、血糖値の急上昇を防いでくれるため食後高血糖になりにくいです。
また、腸内環境を良くする効果も期待できるため、便秘解消につながったり、肌をきれいにしたりする効果も期待できます。
特にキャベツや、キノコ、海藻類などには、食物繊維が豊富に含まれているので同じ量を食べても血糖値の上昇が緩やかで、血糖値を下げるホルモンを出している膵臓の負担も軽くてすみます。


⑤3食(もしくは自分に合った食事の回数)規則正しく食事をしましょう
3食規則正しく食事を摂ることも、血糖コントロールをよくするために重要です。
特に朝食でしっかりと食事をすることは、昼食の際血糖値の急上昇を防ぐことができ、空腹で集中力が低下することもなくなる、など日中のパフォーマンス向上につながります。

朝食後に下がった血糖値はお腹を空かせる原因となり、
その後暴飲暴食の原因となったり、間食をすることにより、血糖の急上昇をする場合があります。
⑥ゆっくりよく噛んで食事をしましょう
早食い、噛まない食事をすると満腹感を感じるタイミングが遅くなり食べる量が増えたり、栄養を急激に吸収したりしてしまうことにより血糖値急上昇のきっかけになります。

ゆっくりよく噛んで食事をすることは、胃腸の負担を敬遠することにもつながるため、体調を整えるという点でも大切となります。
![]() 目標は1口30回を目安にすると良いかと思います。
目標は1口30回を目安にすると良いかと思います。
⑦主食(ご飯・パンなど)の量を一定にしてみましょう
血糖値の急上昇に大きく関係するのは主食などの糖質です。
主食の量を一定にすることによって、自分自身で食事のコントロールがしやすくなり、さらに血糖値をコントロールしていくことにとっても、良い方法です。
![]() 大体握りこぶしくらいの量が毎食取れると良いのではないか、と考えています。
大体握りこぶしくらいの量が毎食取れると良いのではないか、と考えています。
また、お米を「玄米」や「五分づき」とか「七分づき」などちょっと胚芽を入れたものにするとか、パンは精白したものでなく、全粒粉にするとかそういった工夫にするだけでも血糖の上がり方は大きく違ってきます。

まとめ
いかがでしたか?
基本的な食事療法にすでに取り組んでいる方はこのまま継続して、
取り組んでいなかったと思われる方は取り組めそうなところから取り組んでみると良いかと思います。
間食の取り方について
上記の基本的な食事に加えて、間食を意識することもとっても重要なポイントです!
間食には血糖値の上昇の原因となる「糖質」が多く含まれているものが多いです。
• フルーツジュース
• 菓子パン
• ポテトチップス
• おせんべい
• チョコレートなど

こういったものを食べると血糖値が急激に上がって気持ちいいですよね^^
私自身もこういった血糖をあげる食べ物は大好きですが、毎日食べすぎていたら糖尿病、高血圧、高コレステロール血症、肥満などの病気になりますよね。
![]() フルーツジュースや、菓子パン、ポテトチップスなどは頻繁に食べない、あるいは1回の量を少なくするあるいは食事を食べた後に少量にするなどの工夫をすることで違ってくると思います。
フルーツジュースや、菓子パン、ポテトチップスなどは頻繁に食べない、あるいは1回の量を少なくするあるいは食事を食べた後に少量にするなどの工夫をすることで違ってくると思います。
またフルーツジュースを飲むよりは、りんご、パイナップルなど食物繊維が含まれている果物にすることで血糖値の上昇は変わってきます。

こういった考え方を身に付けておくことで、糖尿病の治療だけでなく、コレステロールの上昇を防ぐ、高血圧の予防にも役立ちます。
健康チェックはぜひ当院へ
糖尿病や生活習慣病の予防は、早期の対応が重要です。
当院では、あなたの健康をサポートするために、最新の医療情報と親身な対応で、一人ひとりに合った予防策を提供しています。
単に病気の診断を行うだけでなく、生活習慣の見直しや、健康管理のアドバイスを通じて、患者様が健やかな生活を送れるようお手伝いします。
当院で提供している主なサービスには、以下のものがあります

血糖コントロールがうまくいかない方へ
糖尿病治療は「正しい知識」と「継続できるサポート」で変わります。
あまが台ファミリークリニックでは、医師と管理栄養士がチームであなたを支えます。
まとめ
糖尿病を予防・改善するための食事療法には、多くの科学的根拠があります。
今回ご紹介した7つのポイント(栄養バランス、腹八分、食品の種類、食物繊維、規則正しい食事、よく噛む、主食の量の調整)は、すべてガイドラインにも沿った内容であり、実践することで将来的な合併症のリスク軽減にもつながります。
食事を見直すことは、薬の量を減らしたり、服薬を回避できる可能性を高めるだけでなく、日々の体調や生活の質の向上にも貢献します。
糖尿病予防や血糖コントロールをしたい方は、無理のない範囲で今回ご紹介した内容から始めてみてください。
参考文献
- 日本糖尿病学会編. 『糖尿病診療ガイドライン2024』. 南江堂, 2024年.
- 厚生労働省. e-ヘルスネット「食事バランスガイド」. https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-05-001.html
- 藤井達也ほか. 食物繊維摂取と糖尿病リスク: JPHC研究. 『栄養学雑誌』, 2019; 77(4): 210–218.
- Schembre SM, et al. Effects of mindful eating on glucose control: A meta-analysis. J Diabetes Complications. 2020; 34(8): 107625.
- Gillen MM, et al. Dietary fiber and glycemic control: Evidence and practical guidance. Nutrients. 2021; 13(2): 419.
関連ブログ
糖尿病や生活習慣病の予防・改善に役立つブログを以下にご紹介しています。気になるテーマがあればぜひご覧ください。